みなさんこんにちは!静岡県富士市にある小児科、かわむらこどもクリニックです。
今回は風しんの第5期定期予防接種についてお知らせします。
風しんの第5期定期予防接種は、風しんの公的な予防接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性を対象とした、無料の抗体検査と予防接種です。今年度が事業最終年度となるため、まだ受けていない方はお早めにご検討ください。
対象者
・昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性
対象者から除外される方
・過去に風しん抗体検査を受け、抗体があるとされた方
・風しんの予防接種を受けた記録がある方
クーポン券
・検査および接種には、市町村発行のクーポン券が必要です。対象者には、令和6年5月下旬に令和6年度用のクーポン券が発送されています。富士市以外発行のクーポンでも受け付けております。
・令和5年度以前のクーポン券は原則使用できません。
期間
・2025年2月28日まで
検査に必要なもの
・抗体検査クーポン券(令和6年度発行)
・本人確認書類(運転免許証等)
接種に必要なもの
・予防接種クーポン券(令和6年度発行)
・抗体検査結果通知
・本人確認書類(運転免許証等)
費用
・無料
実施場所
・当院で検査および接種が可能です
注意事項
・風しんの予防接種ですが、MR(麻しん・風しん)ワクチンを使用します。
・ネット予約の場合は予防注射からMRワクチンを選択してください、お電話でも受け付けています。
詳細情報
・厚生労働省 風しんの追加的対策について: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/rubella/index_kigyo.html
・富士市 風しん抗体検査・風しん第5期定期予防接種: https://www.city.fuji.shizuoka.jp/kenkou/c0107/rn2ola000001yb5p.html
風しんは、妊婦さんが感染すると、胎児に先天性風疹症候群を引き起こす可能性があります。 まだ受けていない方は、この機会にぜひご検討ください。
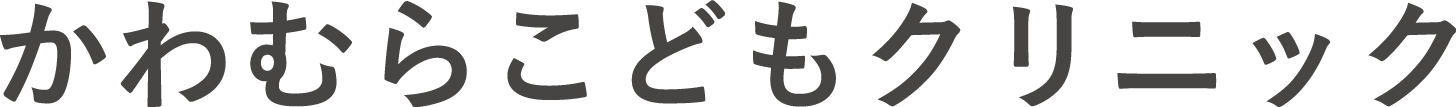
 よくある質問はこちら
よくある質問はこちら ドクター
ドクター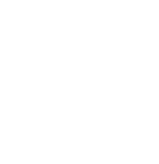 診察
診察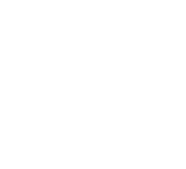 クリニック
クリニック ルート
ルート